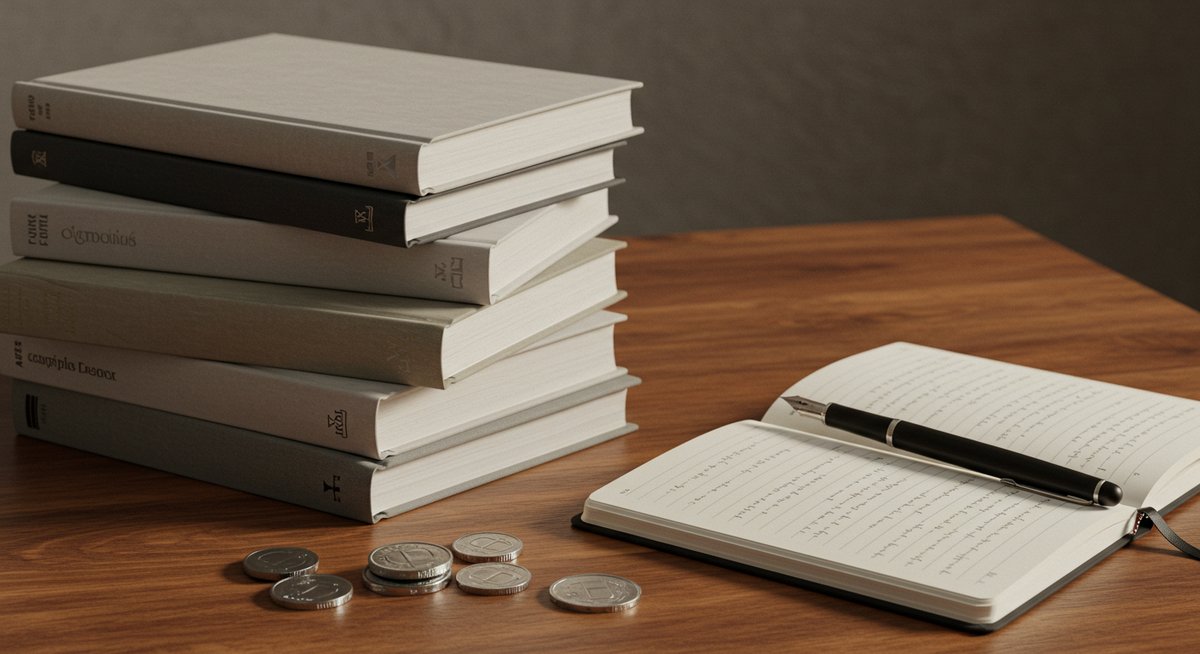小説を書くとき、三人称視点の使い方や特徴について悩む方は少なくありません。自分の物語にどの視点が合うのか、読者に分かりやすく伝えられるのか、不安になることもあるでしょう。
このガイドでは三人称視点の基本からメリット・デメリット、よく起こりがちな失敗例や執筆を支える画材・ツールまで、分かりやすく解説します。視点の技術を身につけて、より豊かな物語づくりに役立ててみてください。
小説の三人称視点とは何かを理解しよう

三人称視点は、作者が登場人物の外側から物語を語る方式です。登場人物の名前や「彼」「彼女」などを使って、客観的に物語を進めていきます。
三人称視点の基本的な種類と特徴
三人称視点には主に「一元視点(限定的三人称)」と「多元視点(複数三人称)」の2つの種類があります。一元視点は、物語全体を一人のキャラクターに密着して進めます。そのキャラクターの思考や感情には深く入り込みますが、他のキャラの内面には触れません。一方、多元視点は、章やシーンごとに視点人物を切り替えて物語を進行できる方法です。
また、まれに「全知視点(神の視点)」を使うこともありますが、これは登場人物全員の心の中や、未来・過去すべてを知っているような語り口です。三人称視点は作者の距離感や情報の出し方を調整しやすく、幅広い物語に応用できます。どの種類を使うかは、物語の展開や読者に伝えたい雰囲気によって選ぶことがポイントです。
一人称や二人称との違いを押さえる
一人称視点は「私」「僕」など、語り手自身の目を通して物語が進行します。読者は語り手の感情や考えを直接体験できる反面、他のキャラクターの内面には触れづらくなります。二人称視点は「あなた」を使い、読者自身が主人公になる形式ですが、小説ではあまり一般的ではありません。
これに対し三人称視点は、語り手が登場人物から一歩引いた立場で物語を伝えるため、より広い視野で状況や他者の行動を描写できます。読者は物語全体を俯瞰しやすく、複数のキャラクターが関わる複雑な物語でも混乱しにくいという特徴があります。どの視点が自分の物語に合うかを意識して選びましょう。
三人称一元視点と多元視点の使い分け
三人称一元視点は、特定のキャラクター一人に密着し、物語を通してその人物の視点で描写します。そのキャラの感情や考えを深く描けるため、読者の共感を呼びやすいです。一方、多元視点では章や場面ごとに主役となるキャラクターを切り替えて進行します。
たとえば、群像劇や複数の主人公が活躍する物語では、多元視点が有効です。ただし、視点切り替えのタイミングや人物の内面描写に注意しないと、読者が混乱しやすくなります。視点ごとに明確な区切りを設け、誰の視点なのかをはっきり伝えることが大切です。
三人称視点が向いている作品ジャンル
三人称視点は、登場人物が多かったり、複数の出来事を同時進行で描きたい場合に適しています。たとえば以下のようなジャンルでよく用いられます。
- ファンタジーやSF
- 推理小説
- 歴史小説
- 群像劇
これらのジャンルでは、登場人物の行動や出来事を客観的に描写し、読者に全体像を伝えやすくなります。複雑な物語構成や広い世界観を持つ作品でも、三人称視点を使うことで、読者が全体を把握しやすくなる点が魅力です。
「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!
著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。
三人称視点のメリットとデメリット

三人称視点には、物語を広く深く描ける良さと、読者や作者がつまずきやすい課題の両方があります。導入しやすい一方、使い方によっては分かりにくくなる場合もあるため、その特徴を知っておきましょう。
客観的な描写がしやすい理由
三人称視点では、登場人物の外から状況を把握できるため、客観的な描写がしやすくなります。読者は語り手に惑わされることなく、物語全体の動きを受け止められます。たとえば、主人公が知らない出来事や背景も表現しやすいです。
また、状況説明や舞台の雰囲気作りにも役立ちます。キャラクターから距離をとることで、世界観や時代背景など、物語の枠組みを丹念に伝えることができます。ただし、客観性が強くなりすぎると、登場人物の感情が伝わりにくくなる場合もあるため、表現のバランスが大切です。
複数キャラクターを描写する利点
三人称視点では、登場人物が複数いる場合にも、それぞれの行動や発言、内面にスポットを当てやすくなります。群像劇や事件を多角的に描きたいとき、効果的な手法です。
たとえば、物語のある場面では探偵、別の場面では犯人側の視点でストーリーを進行できます。これにより、読者は作品の全体像をつかみやすくなり、同じ出来事を異なる立場から見る面白さも生まれます。ただし、視点が頻繁に切り替わると混乱を招くため、章ごとや明確な場面転換に合わせて使いましょう。
感情移入しやすさや読者への距離感
三人称視点は、キャラクターの内面描写や行動両方を描ける一方、読者がキャラクターに感情移入しやすいかどうかは描写方法によります。一元視点の場合、特定のキャラの思考や心情に深く寄り添うことで、読者も同じ目線で物語を体験できます。
その反面、客観的な語りが強すぎると、キャラクターの感情が伝わりにくくなり、読者との距離が広がることもあります。物語の雰囲気や伝えたい内容に合わせて、内面描写の濃淡を調整することが大切です。
三人称視点で起こりやすい混乱や注意点
三人称視点では、視点の切り替えや情報の出し方に注意が必要です。とくに多元視点の場合、読者が「今は誰の視点なのか」を見失いやすい場面が出てきます。
また、キャラクターが知らない情報を不用意に語ってしまうと、物語が不自然に感じられることがあります。視点の統一や、必要な場面ごとに明確な区切りを設け、誰が語り手なのかを常に意識して執筆することが重要です。
三人称視点で魅力的な物語を作るコツ
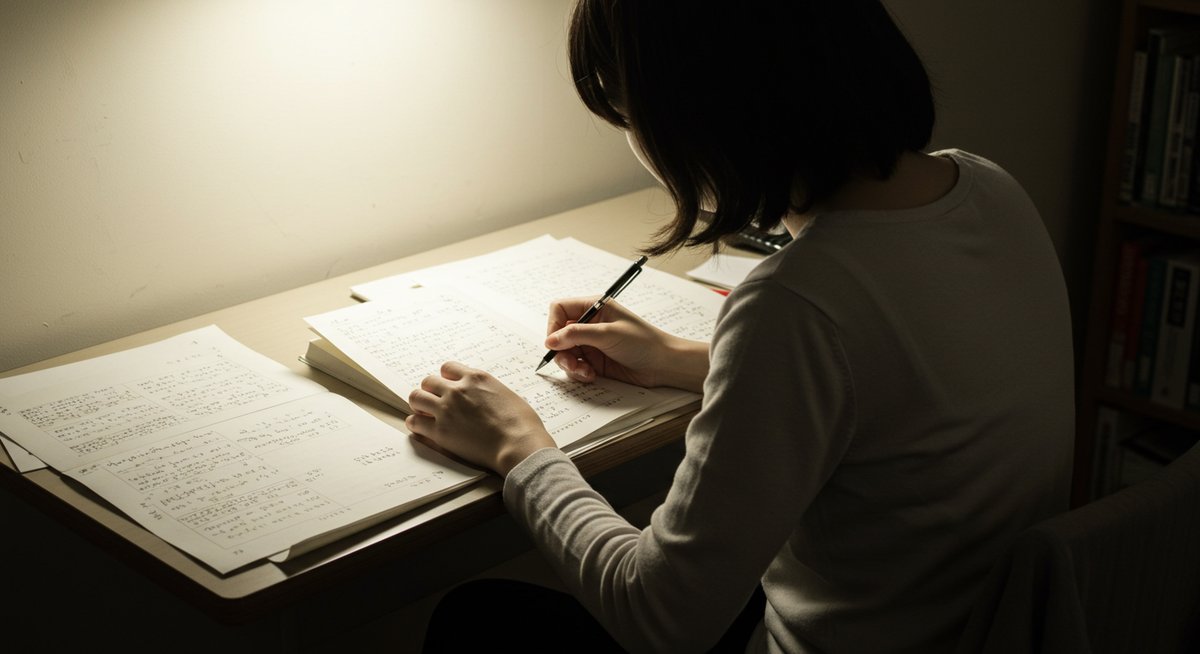
三人称視点を活用して印象的な物語に仕上げるためには、視点の管理や描写の工夫が欠かせません。読者が分かりやすく、ストーリーに入り込めるように気を配りましょう。
視点の統一とブレ防止のポイント
三人称では、視点がぶれると読者の混乱を招きます。特に章やシーンごとに語り手が変わる場合は、その始まりで「誰の視点なのか」を明確に示すことが大切です。
たとえば、「太郎は窓の外を見つめた。彼の心は不安でいっぱいだった」といったように、地の文で視点キャラの思考や感情をさりげなく織り込むと、読者が自然に視点を理解できます。また、同じ場面で複数の内面描写を混ぜないよう意識して執筆しましょう。
シーンごとの視点キャラクター選び
物語の展開や伝えたい情報によって、どのキャラクターの視点を使うかを決めることが効果的です。特定の出来事が誰にとって重要なのかを考えて、その人物の視点から描くと読者が共感しやすくなります。
また、視点キャラごとにシーンを分けることで、物語の流れが整理されます。「この章はAの視点」「次の章はBの視点」といった切り替え方法が定番です。視点キャラの選択には一貫性を持たせ、頻繁に切り替えすぎないように注意しましょう。
内面描写と行動描写のバランス
三人称視点では、登場人物の心情を描く内面描写と、実際の行動や会話を示す行動描写のバランスが大切です。内面描写に偏りすぎると説明くさくなり、逆に行動ばかりになるとキャラクターの気持ちが伝わりにくくなります。
読者がキャラクターの思いを理解しやすいよう、適度に両方の描写を織り交ぜましょう。たとえば「彼女は声を震わせながら謝罪した。その胸には、どうしようもない後悔が渦巻いていた」というように、行動と心情をリンクさせると自然な文章になります。
神視点を避けるための工夫
三人称視点を用いるとき、つい「神の視点」で何でも語りすぎてしまうことがあります。これは、作者がすべてを知っている立場から、登場人物全員の考えや未来までを解説しすぎる状態です。
この問題を避けるためには、視点キャラの知覚や感情だけに限定して情報を伝える意識が重要です。他のキャラクターの心の中までは描写しすぎず、状況や表情などから推測できる程度にとどめましょう。また、「今このキャラは何を知っているか」を常に確認しながら物語を進めていくのがおすすめです。
三人称視点でよくある失敗例と改善方法
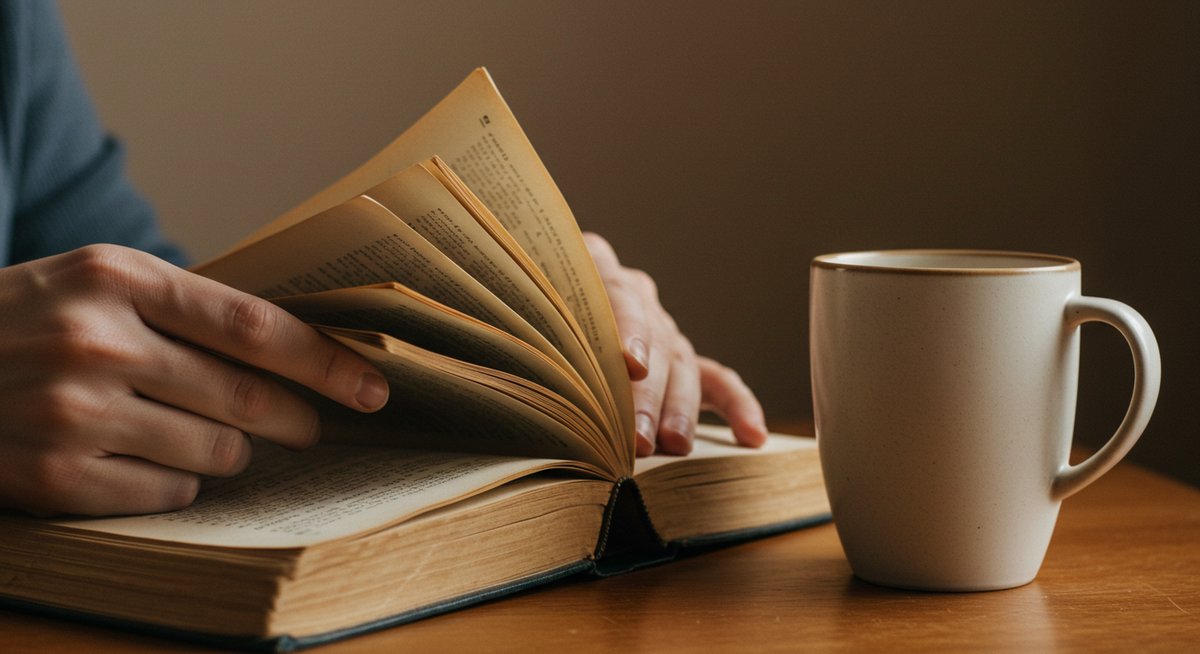
三人称視点で小説を書くときには、混乱や説明過多など、ありがちなミスに気をつける必要があります。代表的な失敗例と、その対処法を押さえておきましょう。
複数キャラの視点が混在してしまうケース
一つのシーンで複数のキャラクターの内面を同時に描写すると、読者が混乱しやすくなります。たとえば「太郎は不安を感じていた。花子はその気持ちを察して内心でほっとした」のような文章を続けると、誰の視点なのかが分かりづらくなります。
改善策としては、シーンごとに一人の視点キャラクターを決め、その人物の感じること・知ることだけを描写しましょう。視点を切り替える必要があれば、段落や章を分けて「今は誰の視点か」を明確に示すのがおすすめです。
読者が混乱しやすい書き方のパターン
視点が分かりにくい表現や、キャラクターの名前・代名詞の使い方が曖昧な場合も、読者は混乱しやすくなります。特に会話が続く場面や、複数人物が同じ場にいるシーンでは注意が必要です。
回避するためには、地の文で「誰が何を感じたか」「今は誰の考えに寄り添っているか」をはっきりさせましょう。場面の最初に視点キャラの行動や思考を記載し、必要に応じてキャラクター名を繰り返すことで、読者にわかりやすくなります。
視点キャラが知らない情報を描写するミス
三人称視点でも、視点キャラが知らない出来事や他人の内面を無意識に書いてしまうことがあります。たとえば「彼は部屋の外で何が起きているか知る由もなかったが、実はそのとき…」といった表現が典型例です。
このミスを防ぐには、「視点キャラがその時点で知ることができる情報だけを描写する」という基本を守りましょう。不明な部分は、後で登場人物の行動や会話を通じて徐々に明かしていく方法が適しています。
小説3人称視点でありがちな説明過多の落とし穴
三人称視点は客観的な語りが可能な反面、ついつい背景や設定を「説明」しすぎてしまうことがあります。これによって物語が冗長になり、読者を飽きさせてしまう場合があります。
説明が多くなりそうなときは、情報を会話やキャラクターの行動に織り込む工夫をしてみましょう。ストーリーの流れに沿って、必要な情報だけを小出しにすることで、テンポよく読み進められる文章を目指せます。
三人称視点で小説を書くためのおすすめ画材と執筆ツール
物語作りをよりスムーズに進めるための画材やツールを活用すると、三人称視点ならではの情報整理や構成作業が効率化します。自分に合ったアイテムを選んで、執筆環境を充実させましょう。
アイデアを整理できるノートやプロットシート
小説のアイデアや物語の流れを整理するためには、ノートやプロットシートが役立ちます。手書きでメモを取ることで、思考を整理しやすくなります。
以下のようなツールがおすすめです。
| アイテム | 特徴 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 無地ノート | 自由に書き込み可能 | アイデアメモや構図 |
| プロットシート | 構成を整理しやすい | 物語の流れ管理 |
| 付箋 | 情報の移動が簡単 | シーン並べ替え |
自分の執筆スタイルに合わせて使い分けると、物語の全体像や登場人物の動きが整理しやすくなります。
キャラクターの把握に役立つチャートやカード
三人称視点では、複数キャラクターの関係や特徴を整理することが重要です。キャラクターチャートやカードを作っておくことで、一人ひとりの情報を見やすく管理できます。
たとえば、登場人物ごとに「名前・年齢・性格・役割」などを記入したカードを作成し、プロットと照らし合わせて使う方法があります。紙のカードやデジタルツールのどちらでも応用できます。物語が進むにつれてキャラの変化も記録しておくと、矛盾や設定漏れの予防にもつながります。
作業効率が上がる執筆ソフトやアプリ
パソコンやタブレットでの小説執筆には、専用ソフトやアプリを活用すると効率が上がります。章やシーンごとに分けて管理できる機能や、アイデアメモとの連携ができるツールが便利です。
たとえば、Scrivener(スクライブナー)やEvernote(エバーノート)などが人気です。クラウド同期ができるものを選べば、外出先でもすぐ執筆やアイデア整理ができます。自分の作業スタイルやデバイスに合わせて、使いやすいツールを見つけましょう。
世界観や場面を可視化するスケッチや資料作り
三人称視点で複雑な世界観や舞台を描く場合、場面のイメージをスケッチしたり、地図や相関図を作るのも有効です。視覚的な資料を手元に置くことで、物語の整合性や臨場感が高まります。
たとえば、物語の舞台となる街や建物の簡単な間取り図を描いたり、登場人物同士の関係を図式化することで、執筆時にすぐ確認できます。デジタル作成ツールとしては、マインドマップアプリやイラスト作成アプリもおすすめです。
まとめ:三人称視点で物語の幅を広げよう
三人称視点は、複数キャラクターや広い世界観を描きやすく、物語の幅を大きく広げてくれる方法です。視点の種類や特徴を正しく理解し、物語のテーマや雰囲気にあった使い分けを意識しましょう。
また、視点の統一やキャラクターごとの描き分け、内面と行動描写のバランスなど、細かな工夫を積み重ねることで、読者にとって分かりやすく魅力的な作品が生まれます。便利な画材や執筆ツールも取り入れながら、理想の物語作りを楽しんでください。
世界70か国で愛されるコピック!
ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。