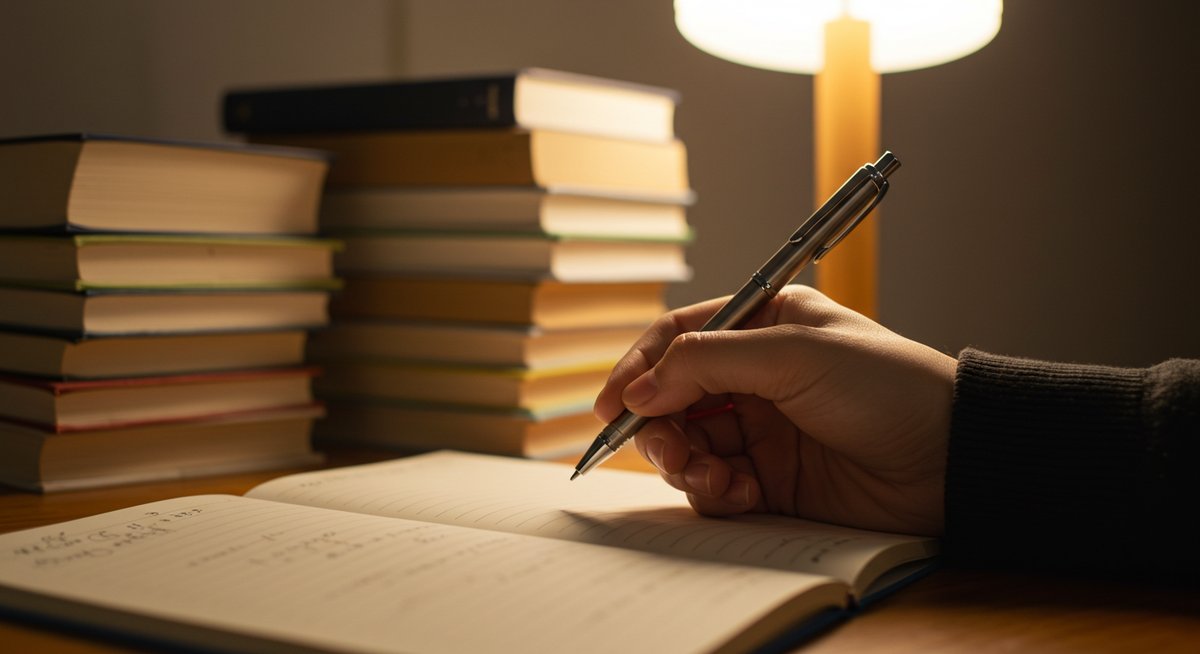小説を読んでいて「なんだか面白くない」と感じたことはありませんか。せっかく物語の世界に入り込みたいのに、途中で興味を失ってしまうのは残念なことです。
読者にとって魅力的な小説とは、どんな物語なのでしょうか。この記事では、つまらない小説にありがちなポイントやその理由、面白い小説との違い、改善策などを具体的に解説します。読者の目線に寄り添いながら、小説づくりのヒントを紹介していきます。
つまらない小説にありがちな特徴とその理由
小説を読んでいると、何となく続きが気にならなくなったり、物語に入り込めないことがあります。これは、つまらないと感じる特徴がいくつか重なって起こっている場合が多いです。
説明や設定が多すぎて物語が進まない
物語の始まりで背景や設定の説明が長すぎると、読者はすぐに物語にのめり込めなくなります。特にファンタジーやSFに多い傾向ですが、「世界の歴史」「登場人物の生い立ち」などを細かく語りすぎると、物語本来の流れが止まってしまいます。
一方で、説明がないと読者が状況を理解できません。このバランスが難しいポイントですが、物語の進行を妨げるほどの情報量は読者の興味を削いでしまいます。物語の流れの中で自然に説明を組み込む工夫が必要です。
主人公やキャラクターの魅力が伝わらない
物語の中心となる主人公や主要キャラクターに魅力が感じられないと、読者は感情移入しづらくなります。性格や行動に一貫性がなかったり、何を考えているのかが分かりづらい場合、「このキャラクターは応援したい」と思えません。
また、特徴がぼやけていると、他の登場人物との差別化も難しくなります。読者が「次はこのキャラクターがどう動くのか」と期待できるような人間らしさや個性を描くことが大切です。
ストーリー展開が予想できてしまう
物語が始まって早いうちに「この先どうなるか」が想像できてしまうと、読者の興味を引き続けるのは難しくなります。ありがちな展開や、パターン化されたストーリー構造が原因で、最後まで読もうという意欲が薄れていきます。
たとえば、困難が起きてもすぐに解決し、主人公が無条件で成功する場面が続くと、緊張感がなくなります。適度な意外性や葛藤があることで、読者は次の展開に期待を持てます。
登場人物が多すぎて覚えにくい
物語の中に登場する人物が多すぎる場合、読者は誰が誰だか分からなくなってしまうことがあります。特に、名前や役割が似ていると混乱しやすく、物語自体への興味も薄れてしまいがちです。
主要な登場人物を整理し、それぞれの個性や役割が明確になるよう意識しましょう。必要があれば、以下のように簡単な表を作ってみてもまとめやすいです。
| 名前 | 役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 主人公A | 主人公 | 正義感が強い |
| 友人B | 親友 | 冷静沈着 |
| 敵キャラC | ライバル | 野心家 |
一貫性のない視点や文体で読みにくい
物語の語り手や視点が頻繁に切り替わったり、文体が章ごとに変わったりすると、読者は混乱してしまいます。特に初心者の方は、一つの視点や語り口で統一した方が読みやすさにつながります。
また、地の文と会話文のバランスが悪い場合も、読みにくさの原因となります。文体や表現を一定に保つことで、物語世界への没入感が高まります。
「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!
著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。
小説がつまらなくなる原因を深掘り
小説がなぜ面白くなくなってしまうのか、その根本的な原因について詳しく考えてみましょう。表面的な特徴だけでなく、物語の仕組みやキャラクターの描き方にも大きな要因があります。
主人公が成長しないまま物語が続く
読者が物語に引き込まれる大きな理由の一つは、主人公が困難を乗り越えたり、内面が変化する過程を見ることです。しかし、物語の中で主人公が最初から最後まで同じまま、成長や変化が見られないと、物語に奥行きが感じられません。
小さな失敗や挫折を経験し、それをどう乗り越えるかを丁寧に描くことで、読者は主人公により深く共感できます。成長がないと「この話を読んで何が残るのか」と感じてしまいやすいです。
ご都合主義な展開でリアリティがない
物語の流れに無理が生じ、作者の都合で事件や出来事が解決してしまう場合、読者は違和感を覚えます。たとえば、「突然の奇跡」で全てが解決する、「重要な情報が都合よく手に入る」などは、物語への没入を妨げます。
リアリティのある展開を心がけ、キャラクターの行動や状況に必然性を持たせることが大切です。ご都合主義を避けることで、物語に説得力が生まれます。
読者の共感を呼ばないキャラクター設定
キャラクターの考え方や行動が現実離れしていたり、極端に一面的な描写しかなかったりすると、読者が感情移入しにくくなります。どんなに特殊な設定でも、「悩み」や「迷い」など、人間らしい部分が描かれていることで共感が生まれます。
読者と年齢や性格が異なっていても、心の動きが丁寧に描かれていれば、物語への関心を維持しやすくなります。
脇役が活かされず物語が薄くなる
物語の中で主人公以外の登場人物がただの「背景」となってしまい、個性や役割が感じられないと、作品全体の印象が薄くなります。脇役がしっかり動き、物語に関わることで、作品に厚みが生まれます。
たとえば、脇役の行動が主人公に影響を与えたり、サブストーリーが物語全体のテーマに関わってくると、より豊かな作品になります。
プロットや構成のバランスが崩れている
物語の展開が偏っていたり、クライマックスまでの流れが不自然だったりすると、読者は物語についていけなくなります。序盤ばかり丁寧で中盤以降が急ぎ足、または逆に中だるみが長い場合も注意が必要です。
物語の構成を見直し、どの場面にどれだけの分量や描写を割くかを考えることで、読みやすく引き込まれる小説に近づきます。プロットの段階で紙やメモに流れを書き出すのもおすすめです。
面白い小説との違いを知ろう
つまらない小説と面白い小説には、いくつかはっきりとした違いがあります。これらのポイントを意識することで、物語づくりのヒントが見えてきます。
オリジナリティよりもアレンジの工夫が大切
完全な独自性を求めて珍しい設定や世界観にこだわりすぎると、逆に分かりづらい物語になることがあります。読者が物語に入りやすいのは、どこか親しみやすい要素がうまくアレンジされているときです。
既存のテーマや王道の展開に、作者ならではの工夫や視点を加えることで、個性的でありながら共感しやすい物語になります。
王道パターンを効果的に活用している
面白い小説の多くは、王道と言われるストーリー展開やキャラクター関係をうまく活用しています。たとえば「成長物語」「恋愛」「ライバルとの対決」など、読み手が親しみやすい要素を取り入れることで、読者は物語に安心感を覚えます。
王道要素だけで終わらせるのではなく、そこに小さなひねりやキャラクター独自の動機を加えることで、より魅力的な作品になります。
読者を引き込むテンポやリズムがある
物語の展開がスムーズで、無駄な説明や場面転換がない点は面白い小説の特徴です。文章の長さや会話のバランスがよく、読み進めやすいテンポを意識することが重要です。
また、重要な場面をじっくり描き、日常の場面は簡潔に済ませるなど、緩急をつけたリズムも読みやすさにつながります。
キャラクターの目的や動機が明確
登場人物がなぜ行動するのか、その動機がはっきりしている小説は、読者にとっても理解しやすくなります。主人公だけでなく、脇役や敵キャラにも目的が設定されていることで、物語に立体感が生まれます。
キャラクターがしっかりと「なぜこれをするのか」と考えて動いていると、ストーリーも自然と引き締まります。
衝撃や意外性のある展開が用意されている
読者の予想を裏切るような展開や、思わず「そう来たか」と感じさせる仕掛けがあると、物語の印象が強く残ります。意外性は無理に狙う必要はありませんが、小さな驚きの積み重ねが大きな魅力になります。
サプライズだけでなく、登場人物の意外な行動や、物語の核心に迫る描写など、読者の気持ちを動かす要素を意識しましょう。
つまらない小説から脱却するための改善策
小説をもっと面白くするためには、どのような工夫ができるのでしょうか。具体的な改善策を紹介します。
プロット作りや構成をしっかり練る
物語の流れやクライマックス、登場人物の関係をあらかじめ考えておくことで、読みやすくまとまりのある小説になります。大まかな流れや重要なポイントを整理しましょう。
プロットづくりの際は、次のような観点でチェックすると良いです。
- 物語の始まり・中盤・終わりは明確か
- 主人公や重要人物の目標がはっきりしているか
- 途中で話が脱線していないか
構成を固めることで、中だるみや唐突な展開を防ぐ効果も期待できます。
キャラクターの個性と成長を意識する
登場人物それぞれの性格や特徴を明確に設定し、物語の中で少しずつ成長や変化がみられるように描くことが大切です。キャラクターごとに「どんな目標があるのか」「どんな悩みを持つのか」を整理すると、自然な行動やセリフを考えやすくなります。
また、主人公が困難に立ち向かい、失敗や葛藤を乗り越えていく過程を丁寧に描写しましょう。読者が「このキャラクターを応援したい」と思えるような工夫が重要です。
無駄な説明や設定語りを削る
物語の進行に直接関係ない説明や背景設定は、なるべく削りましょう。読者がストーリーの流れに集中できるよう、重要な情報だけを厳選して伝える工夫が必要です。
特に冒頭部分では、設定の説明を控えめにし、物語の動きやキャラクターの行動を通じて自然に情報を示しましょう。説明が多すぎる場合は、あとから削ることも大切です。
読者視点で推敲し違和感をチェックする
一度書き上げた原稿も、読者の立場になって読み直すことで、分かりにくい部分や説明の過不足に気づきやすくなります。声に出して読んでみたり、第三者に読んでもらうのも効果的です。
気になる部分は遠慮なく修正し、文章のテンポやキャラクターの違和感がないかを丁寧に確認しましょう。推敲は面倒に感じることもありますが、作品の質を高める重要な工程です。
別ジャンルや他作品からアイデアを取り入れる
自分が普段読まないジャンルや、人気のある小説、映画などからインスピレーションを得るのも、小説づくりの幅を広げる方法です。異なるジャンルの要素を組み合わせることで、新しい物語が生まれることもあります。
読者の立場で「この展開は面白い」と感じた部分を自分の作品にアレンジしてみることで、独自性と面白さの両立がしやすくなります。
まとめ:つまらない小説を面白く変えるために大切なこと
小説がつまらないと感じられる理由や、面白い作品との違い、さらには改善策までを解説しました。すべての読者を満足させるのは難しいですが、物語の流れやキャラクターの魅力、バランスの取れた構成を意識するだけでも作品は大きく変わります。
物語づくりに悩んだときは、一度初心に戻って「読者がどんな部分に興味を持つか」「どうすれば感情移入できるか」を考えてみましょう。地道な積み重ねが、面白い小説づくりにつながります。
世界70か国で愛されるコピック!
ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。