漫画やイラストを描くとき、「思い通りに描けない」と感じることは多いものです。どんな画材を使えばいいのか、どう練習を進めたらいいのか悩んでいる方も少なくありません。
また、他の人と比べて自信をなくしたり、スランプを感じて手が止まってしまうこともあります。
この記事では、漫画やイラスト制作に役立つ画材選びのコツや練習方法、モチベーション維持のヒントまで、初心者から経験者まで参考になる情報を丁寧にまとめました。自身の成長を感じながら、楽しく描くためのヒントを見つけてください。
絵が思い通りに描けないと感じる主な理由

絵がうまく描けないと感じる背景には、さまざまな要因があります。自分がどの部分でつまずいているのかを知ることで、具体的な対策を考えやすくなります。
完成イメージを明確に持てていない
描き始める前に完成形がぼんやりしていると、途中で迷いや違和感が出やすくなります。頭の中で描きたいシーンやキャラクターのイメージがはっきりしていないと、線や色選びに自信が持てず、思い通りの作品に仕上がりにくくなります。
このような場合、まずはざっくりとしたラフスケッチやメモを描くことで、イメージを形にすることが大切です。参考資料や好きな作品を集めてイメージボードを作るのも有効です。完成像が少しずつ見えてくることで、手も動きやすくなります。
技術や知識がまだ足りていない
思い通りに描けない理由の一つに、基本的な技術や知識の不足が挙げられます。例えば、人体の構造や遠近法、光と影のつけ方など、基礎がしっかり身についていないと、頭の中にあるイメージを紙に落とし込むのが難しくなります。
自分が苦手と感じる部分を明確にして、少しずつ練習を重ねていくことが大切です。参考書や動画を見ながら模写をしたり、パーツごとに練習することで、徐々に表現の幅が広がります。
インプットとアウトプットのバランスが崩れている
たくさんのイラストや漫画を見てインプットしているのに、なかなか自分の絵が上達しないと感じることがあります。これは、「見ること」と「描くこと」のバランスが偏っていることが原因かもしれません。
理想的な学び方は、良い作品を観察しながら、それを自分なりに描いてみることです。
箇条書きにすると下記のような流れがおすすめです。
- 気になる作品や作家をピックアップする
- ポーズや構図を真似して描いてみる
- 描いた後に、自分の絵と参考作品を見比べて気づきをメモする
このサイクルを繰り返すことで、インプットとアウトプットのバランスが整い、表現力も育ちやすくなります。
他人と比較して自信をなくしてしまう
SNSやイラスト投稿サイトなどで、他の人の作品と自分の絵を比べて落ち込むことはありませんか。自分よりも上手な人を見ると、やる気を失ったり、描くこと自体が苦しく感じられてしまう場合もあります。
しかし、他人との比較は成長のきっかけにもなりますが、過度に意識すると自信喪失につながります。
「過去の自分と比べて成長しているか」を意識することが、前向きに続けるコツです。自分だけのペースで、一歩ずつ進んでいくことが大切です。
「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!
著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。
漫画やイラストで使う画材の選び方とその特徴
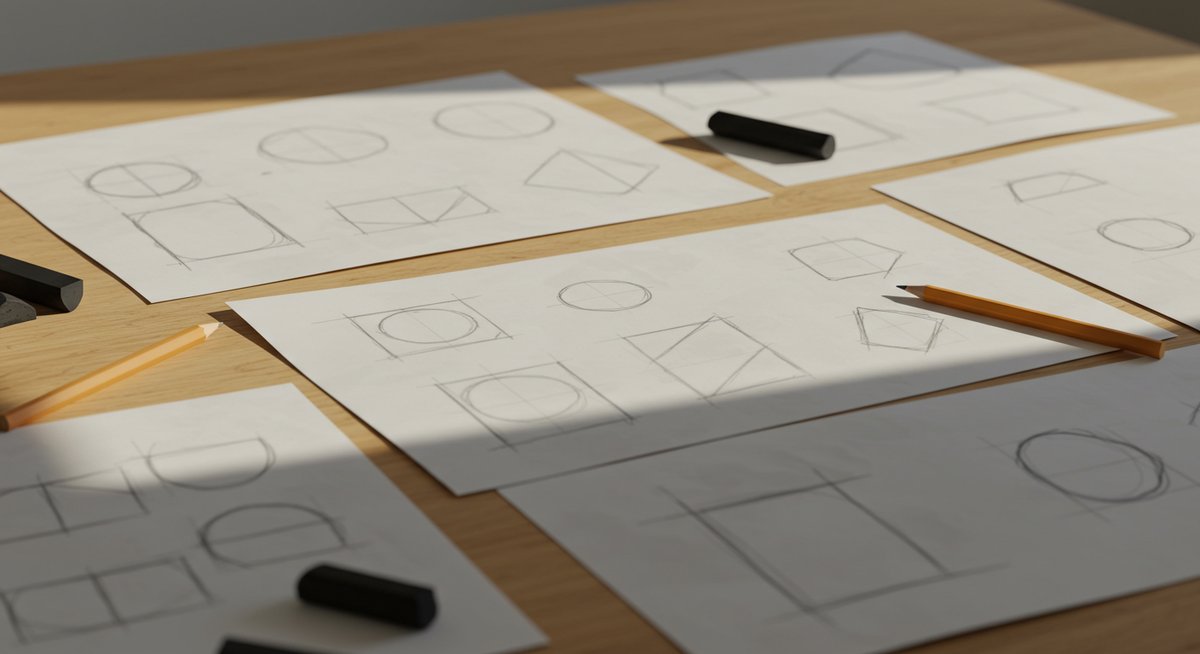
自分に合った画材を選ぶことで、イラストや漫画制作がもっと楽しくなります。ここではアナログからデジタルまで、それぞれの画材のポイントを紹介します。
初心者におすすめのアナログ画材
アナログ画材は実際に紙やキャンバスと手で触れ合いながら描くため、描き心地や発色の良さが魅力です。初心者が扱いやすいものを中心に選ぶことで、ストレスなく上達を目指せます。
例えば、鉛筆やシャープペンシルは線の太さや調子を変えやすく、下書きやスケッチに最適です。消しゴム付きのものを選ぶと、修正がしやすくなります。色をつけたい場合は、色鉛筆や水彩色鉛筆が手軽に使えるでしょう。コピックなどのマーカーも、発色が良くて扱いやすいため人気があります。
以下は初心者におすすめの画材例です。
| 画材名 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| 鉛筆 | 書き心地が柔らかい | 下書き、スケッチ |
| 色鉛筆 | 淡い色から濃い色まで | 塗り、イラスト |
| 水彩色鉛筆 | 水でぼかしができる | イラスト、着色 |
シンプルな画材から始めて、慣れてきたら少しずつ種類を増やしていくのもおすすめです。
デジタル制作に便利なツールとソフト
近年はデジタル制作の環境が整ってきており、パソコンやタブレットとペン型の入力デバイスを使って描く人も増えています。デジタルならではの便利機能が多く、繰り返し修正しやすい点も魅力です。
デジタル制作の主なツールには、液晶ペンタブレットやiPadなどのタブレット端末が挙げられます。ソフトウェアにはクリスタ(CLIP STUDIO PAINT)、アイビスペイント、メディバンペイントなど、多彩な機能を持つものが用意されています。いずれもレイヤー機能やブラシの種類が豊富で、初心者でも直感的に描ける操作性を持っています。
自分が使いやすいデバイスやソフトを選ぶこと、そして最初は無料やお試し版を利用して慣れるのがポイントです。動作の軽いソフトや、スマホ対応のものもあるので、ライフスタイルに合わせて選択肢を広げてみてください。
作品の雰囲気に合う画材の選び方
画材によって、完成した作品の雰囲気や質感は大きく変わります。自分が表現したい世界観やキャラクターのイメージに合わせて、適した画材を選ぶことが重要です。
たとえば、線がくっきりした漫画風の絵を描きたい場合は、ミリペンやインクペンが適しています。やわらかい色合いや、水彩らしいにじみを表現したい場合は、水彩絵の具や水彩色鉛筆がおすすめです。マーカーやパステルは鮮やかな発色や独特の柔らかな仕上がりを出せます。
以下のような選び方が参考になります。
- くっきり線、はっきりした色 → ミリペン、コピック、デジタル
- 淡い色調、ふんわり感 → 水彩絵の具、ソフトパステル
- 重厚感・立体感 → 油絵具、アクリル絵の具
実際にいくつか試してみて、自分の作品に合うものを見つけるのも、描く楽しみの一つです。
画材ごとのメリットとデメリット
画材にはそれぞれ良いところと、注意したい点があります。用途や好みに合わせて使い分けてみましょう。
| 画材 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| アナログ | 手触り・表現の幅が広い | 修正しにくい |
| デジタル | 修正や加工が手軽 | 機材の初期投資が必要 |
| マーカー | 発色が鮮やか | 裏写りしやすい |
アナログは紙の質感や筆圧が伝わりやすく、描いている手応えが直に感じられますが、失敗したときの修正が難しい点もあります。デジタルは「戻る」「消す」などの機能が便利ですが、機材を揃えるコストがかかる場合もあります。マーカーは色塗りが早く、鮮やかな仕上がりですが、紙選びに注意が必要です。
思い通りに描けるようになるための練習法

絵が思い通りに描けるようになるには、日々の練習が欠かせません。ここでは、実践しやすい練習法やテクニックを紹介します。
資料や参考を活用した描き方
描きたいものを上手に描くには、資料や参考画像を活用することが大切です。実際の写真や、好きなイラストを参考にしながら描くことで、リアリティと説得力のある絵に仕上がります。
「資料を見て描くことはズルではないか」と考える人もいますが、プロのアーティストも資料を活用しています。ポーズ集や風景写真、動物図鑑など、描きたいテーマごとに資料を集めておくと便利です。描き始める前にざっと資料を眺め、特徴やポイントを押さえておくと、描写が楽になります。
基礎練習で身につくテクニック
絵の上達には、基礎練習が欠かせません。たとえば、まっすぐな線を引く、円や四角形など基本の形を繰り返し描くことで、手の動きが安定してきます。
また、影のつけ方や立体感の表現を練習するのも効果的です。光が当たってできる影を意識しながら、シンプルなモチーフ(リンゴや箱など)を描いてみると、自然な陰影の付け方が身についていきます。基礎がしっかりすると、複雑なキャラクターや背景も描きやすくなります。
失敗を恐れず描き続けるコツ
練習の途中で「うまくいかない」「思った通りに描けない」と感じることがあっても、失敗を恐れず手を動かし続けることが大切です。失敗した箇所は、今後の課題やヒントになります。
「失敗は成長の材料」と考えて、何度も描き直したり、違う方法を試してみましょう。
たとえば、同じモチーフを数回描いてみる、短時間でラフにたくさん描くなど、自由な発想で練習を続けると気持ちも楽になり、上達につながります。
観察力を鍛えるトレーニング
絵を描く上で「観察力」はとても重要です。普段見慣れているものでも、よく観察してみると意外な発見があります。
たとえば、日常の中で身近な物体や人の動きをじっくり観察し、スケッチしてみましょう。見えている形や、光の当たり方、質感などを意識することで、表現の幅が広がります。観察した内容をメモや簡単なラフに残す習慣をつけると、イラスト制作にも生かせるようになります。
描けないスランプやモチベーションの乗り越え方

誰もが一度は経験するスランプ。描く気力がわかない時期や、モチベーションが続かない時も、工夫次第で前向きな気持ちを取り戻せます。
スランプ時の気持ちの切り替え方法
スランプに陥ったときは、「今は休む時間」と割り切ることも大事です。無理に描こうとすると、余計に苦しくなってしまうこともあります。
しばらく絵から離れて好きな音楽を聴いたり、美術館に足を運んだりと、普段と違う体験をしてみましょう。そのうち気持ちに余裕ができ、再び描きたくなるタイミングが訪れます。焦らず自分のペースを大切にしましょう。
楽しく継続するための工夫
「楽しい」と感じる瞬間があるから、続けることができるのが創作活動です。
飽きずに描き続けるためには、以下のような工夫が役立ちます。
- 好きなキャラクターやテーマに挑戦する
- 新しい画材やソフトを試してみる
- お題やチャレンジ企画に参加する
「描いてみたい」という気持ちを大切にし、自由な発想で取り組むことが長続きのコツです。
他の人との交流や意見の取り入れ方
一人で描き続けていると、時には行き詰まることもあります。そんな時は、他の人と作品を見せ合ったり、感想をもらうと新たな刺激になります。
SNSやイラスト投稿サイトで気軽に交流したり、友人とお互いの絵を見せ合うのもおすすめです。アドバイスや意見を受け入れることで、自分では気づかなかった部分が見えてきます。新しい発見が、再び創作意欲を高めてくれます。
小さな目標設定で達成感を得る方法
大きな目標を掲げてしまうと挫折しやすくなります。小さな目標を設定することで、達成感を積み重ねることができます。
たとえば、「今日は10分だけ描く」「1日1枚ラフを描く」など、無理のない範囲で目標を決めましょう。達成できたら自分をしっかり褒めて、次へのモチベーションにつなげることが大切です。
上達を加速させる実践的なアドバイス
これからさらに絵が上達したい方に向けて、実践しやすいアドバイスをまとめました。日々の練習や工夫の参考にしてください。
描けるものから始めて成功体験を積む
最初から難しいものに挑戦すると、うまくいかずに挫折してしまいがちです。まずは、自分が得意なモチーフや、簡単に描けるものから始めてみましょう。
「描けた!」という達成感を重ねることで、自然と自信がついていきます。少しずつ難易度を上げていくことで、成長を実感でき、継続もしやすくなります。
様々な画風やアーティストの模写を試す
自分のスタイルや表現の幅を広げるには、いろいろな画風や有名アーティストの模写に挑戦するのも効果的です。模写を通じて、線の使い方や色使い、構図など新しい発見がたくさんあります。
自分にはなかった描き方やアイデアを吸収することで、自然と表現力も向上します。模写した作品は、必ず「参考にした作家名」を明記するなど、マナーを守って取り組みましょう。
描きたいテーマやジャンルを明確にする
「何を描いていいかわからない」という時は、まず描きたいテーマやジャンルを明確にしてみましょう。ファンタジー、日常風景、人物、動物など、ジャンルを決めることで、具体的な練習や資料集めがしやすくなります。
自分がワクワクするテーマを見つけることが、創作のモチベーションにもつながります。テーマを決めて小さなシリーズに取り組むのもおすすめです。
プロや経験者からアドバイスを受ける方法
独学だけでは気づきにくいポイントも多いため、プロや経験者からアドバイスをもらう機会を作ると効果的です。
- イラスト講座やワークショップに参加する
- SNSで気になる作家に質問してみる
- 作品投稿サイトでコメントをもらう
自分とは違う視点や専門的なコツを教わることで、新たな発見や上達へのヒントが得られます。積極的にコミュニケーションを取ることも大切です。
まとめ:自分らしく描く楽しさと成長のコツ
絵や漫画を描く楽しさは、自分の世界を自由に表現できることにあります。他人と比べすぎず、自分らしいペースで取り組むことが、長く続けるポイントです。
画材選びや練習法、モチベーション維持の工夫を取り入れながら、小さな成功体験を積み重ねていきましょう。自分だけの成長や発見を大切にしながら、楽しみながら描き続けてください。
世界70か国で愛されるコピック!
ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。












