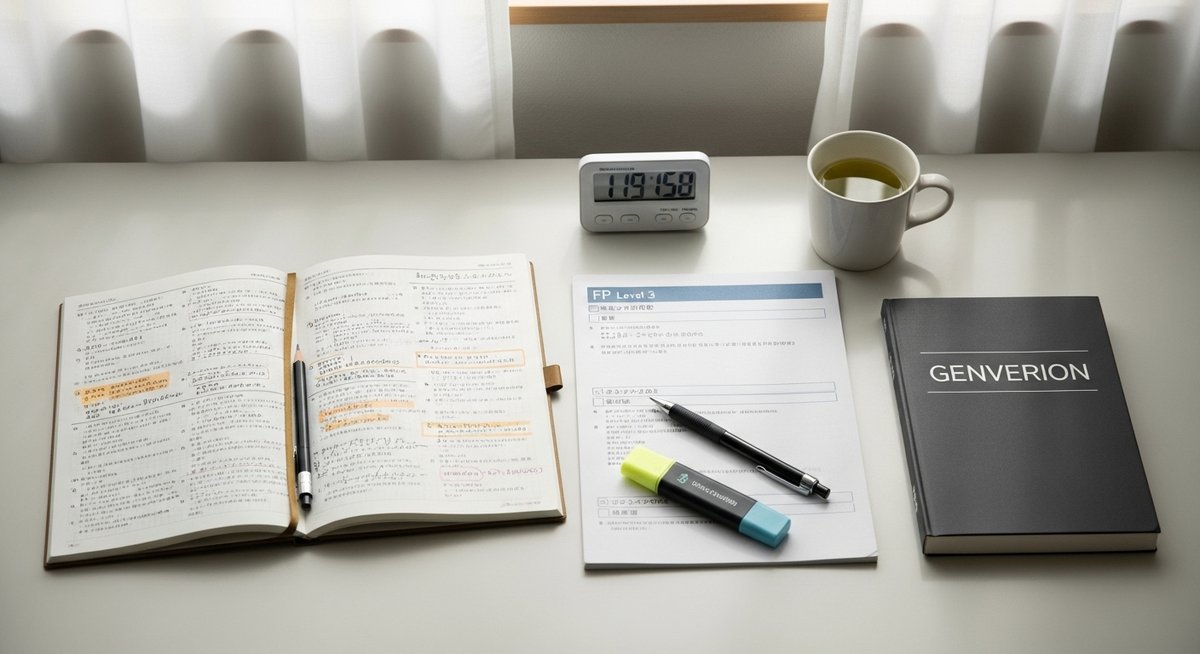FP3級の合格を目指すなら、学習の全体像とノートの扱い方を最初に決めると効率が上がります。短期間で点を伸ばすには、必要な勉強時間を押さえ、問題演習を中心に回すことが大切です。ノートは書きすぎず、見返しやすさを重視して作ると復習がはかどります。これから紹介する流れを参考に、自分に合った計画とノート運用を始めてください。
FP3級の勉強方法とノートで合格にぐっと近づける短期プラン
必要な総勉強時間と学習期間の目安
FP3級合格に必要な総勉強時間はおおよそ50〜100時間が目安です。基礎知識の理解と過去問演習のバランスによって幅は出ますが、初学者なら80時間前後を見込むと安心です。
学習期間は3か月プランが無理なく継続できる設定です。週に6〜8時間を確保すれば、基礎→応用→過去問確認の流れを踏めます。短期で詰める場合は1か月で集中的に50〜60時間を確保しますが、計画的に休憩と復習時間を入れて疲労をためないようにしてください。
仕事や家事と両立する場合は、1日30分〜1時間の学習を継続する戦略が有効です。細切れ時間を活用して公式や用語を繰り返すだけでも確実に力になります。週末にまとまった演習時間を入れて、学んだことを問題で確認するサイクルを作りましょう。
おすすめの教材と使う順番
教材選びは、まず全体像を押さえられる教科書、次に過去問中心の問題集、最後に補助教材として動画やアプリを組み合わせるのが効率的です。教科書は要点が整理されているものを1冊選び、まず一通り読み進めます。
次に過去問集を使って出題パターンに慣れます。過去問は年度別やテーマ別に分かれているものが便利で、間違った問題はノートにまとめます。計算問題は問題集の演習を繰り返し、途中式をノートに残すと後で見直しやすくなります。
補助として動画は短い解説を補う目的で使用します。通勤時間や休憩時間にアプリで用語やミニ問題を解くと知識が定着します。教材は多すぎると迷うので、必要最低限に絞って反復することを優先してください。
ノートは最小限にして復習を中心にする理由
ノートを作る目的は「見返して記憶を定着させること」です。情報を詰め込みすぎると見返す気が失せるため、要点や間違いを抜き出したコンパクトなノートにするのが効果的です。見開き1ページで分かる単位でまとめると使いやすくなります。
復習中心にする利点は、短時間で効率よくインプットとアウトプットを繰り返せる点です。学習後すぐにノートを見直し、1日〜1週間後に再確認するサイクルを作ると記憶が残りやすくなります。ノートは問題を解いた記録や解法のコツ、間違えた理由を中心に書いておくと復習がスムーズです。
書き方は短い箇条書きや表、図を取り入れて視覚的に整理すると効果が高まります。色分けは過剰にしないで、苦手分野を判別しやすい程度に抑えてください。
計算問題は手で繰り返し解いて慣れる方法
計算問題は解法の流れを手で書いて覚えることが重要です。まずは教科書や解説を見ながら一度自分で手を動かして解き、次に同じ問題を時間を計らず再現する練習を行ってください。途中式を書き残す習慣をつけると、どこでミスしたかが分かりやすくなります。
慣れてきたら本番を想定して時間を計る練習を行います。時間配分を身につけることで焦らず解けるようになります。間違えた問題は解き直してノートにまとめ、同じミスを繰り返さないように管理します。
また、計算パターンを分類しておくと応用力がつきます。例えば税金や保険料など分野別に解法の骨格をノートにまとめ、短時間で見返せるようにしておくと効率的です。
試験直前に確認するノートの箇所
試験直前は広く学んだ内容を詰め込むより、すぐ見返せる箇所をチェックすることに集中します。重要公式の見開き、よく出る用語一覧、間違いノートの抜粋を最優先で確認してください。
計算が多い分野は代表的な問題の途中式と解法の流れをざっと見直します。記憶があいまいな用語や語句は単語カード感覚で目を通すと安心感が出ます。精神的な落ち着きも点に影響するので、前日は無理に新しい範囲を詰め込まず、ノートのまとめ部分を軽く確認して休むようにしてください。
「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!
著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。
FP3級の勉強で使う教材とノートの中身
教科書でまず全体像を把握する
教科書はFP3級の全体像を短時間でつかむための最初のツールです。分野ごとの構成や頻出テーマを把握することで、後の問題演習で何を重視すべきかが見えてきます。まずは見出しと章末のまとめを読むだけでも大まかな流れがわかります。
読み方のコツは、一度通読して全体を把握した後、重要な箇所に線を引き、要点だけをノートに転記する方法です。全文を書き写す必要はなく、キーワードや公式、図表だけを抜き出すと復習が楽になります。教科書は複数回繰り返し読み、分からない用語はその都度書き留めて解決していってください。
教科書を基盤にして問題演習へつなげると、新しい問題に出会ったときに関連知識を引き出しやすくなります。時間配分を決めて教科書を読み、すぐに問題で確認するサイクルを作ることが大切です。
過去問を中心に問題集を選ぶ方法
過去問は出題傾向をつかむために最適な教材です。まずは過去5年分程度を目安に解いて、頻出テーマや出題パターンを把握しましょう。問題集は解説が丁寧で復習に使いやすいものを選ぶと効率が良くなります。
選び方のポイントは、解説が具体的で途中式や理由が示されているかどうかです。問題集によってはテーマ別にまとまっているものもあり、弱点対策に便利です。問題を解いたら、間違った箇所は分野ごとにノートへ記録し、類似問題を繰り返し解くようにします。
時間配分を意識して、本番形式で過去問を解く練習も取り入れてください。選択肢の読み方、解答根拠の立て方を身につけることで本番での安定感が増します。
動画やアプリを効率よく取り入れる
動画は短時間でポイントを押さえたいときに便利です。通勤時間やスキマ時間に視聴して苦手分野の理解を補完すると学習効率が上がります。解説が分かりやすい講師の動画を選び、テキストと併用して使うと効果的です。
アプリは用語確認やミニ問題の反復に適しています。毎日少しずつ進められる形式が多いので、学習習慣の維持に役立ちます。通知機能を活用して学習時間を確保すると続けやすくなります。
ただし、動画やアプリに時間を取られすぎないよう注意してください。あくまで教科書と過去問を中心に据え、足りない部分を補うツールとして活用するのが良いでしょう。
ノートに書くべき公式と表のまとめ方
ノートには頻出の公式と比較表を簡潔にまとめます。見開き1ページに「税・保険・年金など分野別の主要公式」を並べ、使う場面がわかる注釈を付けると実用的です。表は縦横を揃えて見やすくし、短い説明を付け加えます。
例えば、税金関連は控除の種類、計算の順序、税率の一覧を表にまとめます。保険は保険料の計算方法や給付条件を箇条書きにすると見返したときに理解しやすくなります。色は多用せず、重要度に応じて2色程度で区別すると視認性が保てます。
書き方は端的な言葉でまとめ、余白を残して後から追記できるようにしておきます。公式の導出過程は別ページに整理しておくと、暗記だけでなく理解の確認にも使えます。
紙ノートとデジタルノートの選び方
紙ノートは手で書くことで記憶に残りやすい利点があります。書き心地が良いノートを選び、重要な図や計算式を自在に描ける点が魅力です。一方で検索や編集がしにくい点に注意が必要です。
デジタルノートは検索性や保存性に優れ、写真や動画リンクを貼れるのが便利です。クラウドで管理すればどこでも見返せますが、入力の手間や長文の整理に時間がかかる場合があります。スマホやタブレットで使う場合は、手書き入力対応アプリを選ぶと紙ノートに近い感覚で使えます。
選び方は自分の学習スタイルに合わせてください。基本は紙で重要公式と計算の途中を残し、デジタルで目次や索引、過去問の成績管理を行うと両方の利点を活かせます。
合格へ導く勉強スケジュールの立て方
3ヶ月プランの週ごとの流れ
3ヶ月プランは週ごとに役割を分けると継続しやすくなります。初月は教科書で全体を把握し、基礎用語と公式をノートにまとめる期間に充てます。週あたり6〜8時間を目安に、分野ごとにターゲットを設定してください。
2か月目は問題演習に軸足を移します。過去問や問題集を週ごとに分け、間違いノートを作りながら復習のサイクルを回します。演習は1回解いたら必ず解説を読み、解法をノートに整理する習慣をつけてください。
最終月は模試や過去問の本番想定演習に重点を置きます。時間配分の訓練と、試験直前に確認するノート部分の反復を行い、弱点の最終チェックをします。週末にまとまった実戦演習を入れると本番対応力が高まります。
1か月集中プランの時間配分
1か月で仕上げる場合は週に12〜15時間ほど確保し、短期間で知識と演習を回します。最初の1週目は教科書を集中して読み、主要公式と頻出テーマをノートにまとめます。
2週目以降は過去問を中心に演習し、間違った問題は即ノートに記録します。後半の1週間は本番形式で時間配分を確認し、苦手分野の重点補強を行います。疲労がたまると効率が落ちるため、毎日短時間の復習を欠かさず入れてください。
平日と休日の学習バランス例
平日は短時間で定着を図る学習、休日はまとまった演習に当てると効率的です。平日は1日30〜60分で用語・公式の確認やアプリの演習を行い、隙間時間で知識を積み上げます。
休日は2〜4時間を確保して過去問演習や模試を実施します。解いた後は解説を読み、間違いをノートにまとめる時間も必ずとってください。平日と休日で役割を分けることで無理なく学習量を確保できます。
復習のタイミングとノートの活用法
復習は学習直後、翌日、1週間後の3回を意識すると記憶が定着しやすくなります。学習直後はノートに要点をまとめ、翌日はそのノートを軽く読み返します。1週間後は問題で確認し、必要ならノートを追記します。
ノートは「要点」「間違い」「代表問題」の3つのカテゴリで管理すると使いやすいです。短時間で見返せるよう見開き構成を意識し、頻繁に参照する箇所は付箋やしおりで目印を付けておくと効率的です。
試験前の1週間のチェックポイント
試験前の1週間は新しい範囲に手を出さず、ノートの重要箇所を中心に確認します。重要公式、用語一覧、間違いノートの抜粋を繰り返し見直してください。
また、時間配分の最終確認として過去問を本番形式で1〜2回解くと安心できます。体調管理も重要なので、睡眠や食事に気をつけて直前は無理をしないようにしてください。
ノートの書き方と見返しを習慣にする工夫
重要公式は見開きでまとめる
重要公式は見開き1ページに収め、分野ごとにページを分けておくと見返しやすくなります。一目で使い方が分かるように、公式の前提条件や適用範囲も短く添えてください。
見出しや余白を活用して、すぐに探せる構成にしておくと復習がはかどります。余白には関連例題の番号を書いておくと、該当問題にすぐ戻れます。
計算問題は途中式を整理して残す
計算問題は途中式を丁寧に残すことが重要です。解答だけでなく過程を書いておくと、どのステップでつまずいたかが明確になります。特に税や年金の計算はステップごとの理由を一行程度でメモしておくと見返しが簡単です。
また、類似問題をまとめておけばパターンがつかみやすく、後で短時間で復習できます。間違えた問題は「ミスの種類」も一緒に書くと改善につながります。
苦手分野は色分けで見つけやすくする
苦手分野は目立つ色でマークしておくと、復習時に優先して取り組めます。色は多用しすぎず、例えば赤=要注意、黄色=要復習のようにルールを決めておくと整理がしやすいです。
色分けは紙ノートでもデジタルでも活用できます。視覚的な区別があると学習時間の配分を効率的に行えるようになります。
図や表で視覚的に整理する方法
図や表は情報を短時間で理解する助けになります。フロー図で計算手順を示したり、比較表で選択肢や条件を並べると覚えやすくなります。複雑な説明は短い箇条書きにして図と組み合わせてください。
図はシンプルに保ち、長文は避けるとスマホで見返すときにも読みやすくなります。重要な図はノートの最初の方にまとめておくと使い勝手が良くなります。
すぐ見返せる索引や目次の作り方
ノートの冒頭に目次や索引を作ると探す手間が省けます。分野ごとにページ番号やトピックを短いキーワードで一覧化し、新しく追記した際は随時更新してください。
デジタルノートならハイパーリンク、紙ノートなら色つき付箋でジャンプできるようにしておくと便利です。頻繁に見る項目は付箋で固定しておくと探す時間が減ります。
問題演習とノートを連動させる学習法
過去問は回数を決めて繰り返す
過去問は1回解くだけでなく、回数を決めて繰り返すことで確実に力がつきます。まずは解いて解説を読み、間違いをノートに記録します。一定期間おいて再度同じ問題を解き、正答率が上がるかを確認してください。
繰り返しの目安は同じ問題を2〜3回。特に頻出分野はより多く回すと安心です。回数管理はノートやアプリで記録すると進捗が見える化できます。
間違いノートで弱点を明確にする
間違いノートは問題番号、誤答の理由、正解への導き方を簡潔に書きます。間違いの原因を分類(計算ミス、知識不足、時間配分ミスなど)しておくと対策が立てやすくなります。
ノートは見返すことが目的なので、解説の丸写しは避け、短い要点と再発防止策を書くようにしてください。定期的にこのノートだけを見直す時間を設けると弱点が自然に改善されます。
計算問題は時間を計って本番想定で練習する
計算問題は本番を意識した時間配分で練習することが重要です。通常の演習は解法を確認するための無制限の時間で行い、仕上げ時期には制限時間内で解くトレーニングに切り替えます。
タイマーを使い、時間が足りなかった箇所や焦ってミスした部分をノートに記録しておくと改善ポイントが見えてきます。繰り返していくうちに適切な時間配分が身についてきます。
模試の結果をノートに反映して改善する
模試は現状の実力を測る良い機会です。模試の結果は得点だけでなく、分野別の正答率や時間配分をノートにまとめ、改善策を立てます。模試後は必ず復習時間を確保し、間違いノートに反映させてください。
模試を数回こなすことで試験慣れし、弱点が明確になります。模試の結果を基に学習計画を微調整すると効率が良くなります。
分野別にまとめノートを作る手順
分野別ノートは各分野ごとに重要公式、代表問題、頻出用語をまとめる形式が使いやすいです。作る手順は、教科書や問題集で重要部分を抽出し、短い見出しとともにノートに整理することです。
各分野の最後には「要チェック項目」を箇条書きで入れておき、試験直前にざっと見返せるようにします。分野別のノートは苦手分野の重点学習にも適しています。
FP3級合格へ向けて今すぐ始める勉強とノートの取り組み
今すぐ始めるなら、まず教科書を1周読んで主要な公式と用語をノートにまとめてください。次に過去問を1回解いてみて、間違いノートを作るところから学習を回し始めます。毎日の短い学習と週末のまとまった演習を組み合わせ、ノートを見返す習慣をつければ着実に力がつきます。焦らず継続することが合格への近道です。
世界70か国で愛されるコピック!
ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。