「デッサンに使えるクレヨンみたいな画材ってどんなものだろう?」と悩んだことはありませんか。鉛筆以外でやわらかな表現や色味を加えたいと感じる方は多いものの、クレヨンやパステル、コンテ、クレパスなど似ているようで違いが分かりづらいものです。
どんな種類があって、自分にはどれが合うのか迷いがちですが、それぞれの特徴や選び方を知ることでデッサンがさらに楽しくなります。この記事では選び方や使い方、人気アイテムまで丁寧に解説します。
デッサンに使えるクレヨンみたいな画材の特徴と選び方

デッサンで使えるクレヨンのような画材には、独特の質感や発色、使い心地があります。鉛筆では出せない表現を取り入れたい方に適した選択肢が多く揃っています。
デッサン向きのクレヨンみたいな画材とは
デッサン用に適したクレヨンみたいな画材は、一般的なクレヨンよりも細かい描写や濃淡の表現がしやすいものが多いです。たとえば、パステルやコンテ、クレパスなどが挙げられます。
これらは手触りや描き味がそれぞれ異なり、線を重ねたり、指でぼかしたりと幅広い技法に対応できます。特にパステルやコンテは、やわらかい質感や自然なグラデーションの表現が得意です。自分の描きたい雰囲気や作品の用途に合わせて選ぶことがポイントとなります。
クレヨンとパステルの違いを知ろう
クレヨンとパステルの大きな違いは、素材や描き味にあります。クレヨンは主にワックス(ロウ)を使って作られ、滑らかで丈夫な芯が特徴です。一方、パステルは顔料を糊で固めただけのため、粉っぽく柔らかいタッチになります。
パステルは繊細な色の重ねやぼかし表現がしやすく、自然な陰影や色彩のグラデーションを描くのに向いています。クレヨンは発色がしっかりしており、耐久性もあるのでラフなスケッチや子どものお絵描きにも使いやすいです。自分が求める質感や表現によって、どちらを選ぶかが変わってきます。
コンテやクレパスの特徴と用途
コンテは炭や顔料を固めてスティック状にした画材で、主にデッサンやクロッキーで使われます。黒・茶・白などモノトーンが中心で、線描や陰影の表現に適しています。硬めの質感なので、細い線やシャープな表現が得意です。
クレパスはクレヨンとパステルの中間のような存在で、油分を含んだ柔らかな描き味と鮮やかな発色が特徴です。混色や重ね塗りも楽しめ、幅広い画風に対応できます。下描きから本格的なアートまで幅広く使えるので、好みに合わせて使い分けるのが良いでしょう。
用途や画風に合わせた色数や硬さの選び方
用途や描きたい画風によって、必要な色数や画材の硬さが異なります。たとえば、初心者やシンプルなデッサンには12色程度の基本セットが便利です。複雑な色彩表現を目指す場合は24色以上があると表現に幅が生まれます。
また、硬めの画材は細かい線や描写に向いており、柔らかい画材は広い面を塗ったり、ぼかし表現を行いたいときに便利です。以下の表を参考に、用途と好みに合わせて選びましょう。
| 用途 | 色数の目安 | 硬さのおすすめ |
|---|---|---|
| 基本デッサン | 12色前後 | 硬め(コンテなど) |
| カラー表現 | 24色以上 | 柔らかめ(パステル) |
| 混色や重ね塗り | 24色以上 | やや柔らかめ |
「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!
著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。
クレヨンみたいな画材の種類とそれぞれの魅力

クレヨンのように見える画材は、実はさまざまな種類があります。それぞれの違いや魅力を知って選ぶことで、より自分好みのデッサンを楽しむことができます。
ソフトパステルとハードパステルの違い
ソフトパステルは粉のような質感で、非常にやわらかく色が鮮やかに出ます。広い面を塗ったり、指や綿棒でぼかしたりする表現に向いています。一方、ハードパステルは芯がしっかりしており、細かな描写や線描に適しています。
特にデッサンでは、下描きにハードパステル、本塗りやぼかしにソフトパステルを使うのも一般的です。それぞれの特性を活かして使い分けることで、多様な表現が可能になります。
オイルパステルの発色と表現力
オイルパステルは油分を多く含み、なめらかな描き味と鮮やかな発色が特徴です。重ね塗りや混色もしやすく、透明感のある表現や厚塗りの質感を楽しむことができます。
また、表面がべたつきにくいため手が汚れにくく、初心者にも扱いやすい点が魅力です。子どもから大人まで幅広い層に人気があり、イラストやアート作品の制作にも適しています。
コンテの独特な描き味と使い方
コンテはしっとりとした手触りで、線を描いたり、軽くこすったりして濃淡を表現できます。モノトーン表現が中心なので、陰影や立体感を強調したいデッサンにぴったりです。
使い方としては、芯の先端で細い線、側面で太い面を描き分けられるため、一本で多彩な表現ができます。また、消しゴムで消したり、紙でぼかしたりと、修正や変化も加えやすい画材です。
クレパスが持つ幅広い応用力
クレパスは、発色の鮮やかさや油分によるなめらかさが魅力です。混色や重ね塗りも簡単にでき、イラストやポップなアート作品にもよく使われます。
また、紙以外の素材にも描くことができるため、クラフトや工作など多彩な用途に対応します。手軽に始められ、表現の幅が広がる画材のひとつです。
初心者が知っておきたいデッサン用画材の選び方

初めてクレヨンみたいな画材を選ぶときは、どんなセットやメーカーを選ぶか迷うものです。ここでは初心者向けの選び方のポイントや注意点を解説します。
初心者におすすめのセットやメーカー
初心者には、手頃な価格で品質が安定しているセットがおすすめです。日本のメーカーなら「ぺんてる」や「サクラクレパス」、海外では「ファーバーカステル」や「レンブラント」などが定評があります。
以下のような点を重視して選ぶと失敗が少ないです。
- 色が基本色中心で揃っている
- 持ちやすいサイズ
- ブランドの信頼性
最初から高級品にこだわらず、扱いやすさやラインナップを優先しましょう。
色数とパッケージの選び方
色数は、シンプルなデッサンなら12色程度で十分です。表現に慣れてきたら24色や36色セットを選ぶと、よりバリエーション豊かな作品が描けます。
パッケージもポイントです。持ち運びを重視するなら、スリムな缶ケースやコンパクトな紙箱がおすすめです。自宅での使用が中心なら、収納しやすい大きめのケースも便利です。
画材の安全性やアレルギー対策
画材によっては、アレルギーの原因となる成分が入っている場合もあります。特に子ども用や肌に触れる機会が多い場合は、「APマーク」など安全基準を満たしている商品を選ぶと安心です。
最近は無害な素材を使った画材も増えているので、成分表やメーカーサイトで安全性を確認しましょう。手荒れが気になる場合は、手袋の着用や使用後の手洗いも習慣にすると良いです。
価格帯とコストパフォーマンス
初心者が選ぶ場合、価格と品質のバランスも重要です。安価なセットは手軽ですが、発色や描き味に差が出ることもあります。逆に高すぎる商品は使いこなせない場合もあるので、まずは中価格帯の製品を選ぶと安心です。
セット販売の商品は単品で買うより割安になる場合が多いため、お試し用としてもおすすめです。自分の使用頻度や目的に合わせて、コストパフォーマンスを比較しながら選びましょう。
上達を助けるクレヨンみたいな画材の使い方とテクニック
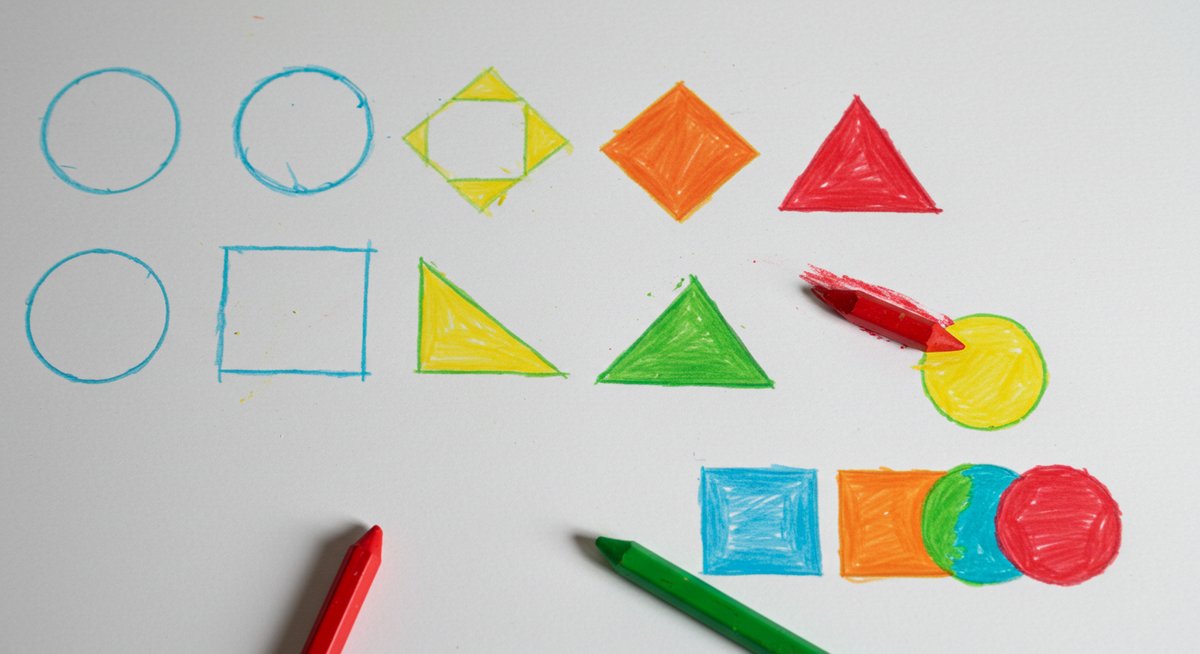
クレヨンみたいな画材を使いこなすことで、デッサンの表現力がぐんと広がります。ここでは、基本的なテクニックやメンテナンスのコツを紹介します。
基本的な塗り方や重ね塗りのコツ
基本的な塗り方には「面塗り」「線描」「重ね塗り」などがあります。面塗りは画材の側面を使って広い面を均一に塗る方法、線描は先端を使って細い線を描く方法です。
重ね塗りをするときは、まず薄い色から順番に重ねていくときれいなグラデーションになります。力を入れすぎず、軽く塗り重ねるのがコツです。画材によっては色が混ざりやすいので、慣れてきたらさまざまな重ね方を試してみてください。
ぼかしや混色で表現を広げる方法
ぼかしは、指や綿棒、ティッシュなどを使って色同士をなじませます。とくにパステルやコンテは、ぼかすことで自然な陰影や立体感を出すことができます。
混色は、隣り合う色を少しずつ重ねたり、ぼかしながらなじませたりして新しい色合いを作る方法です。画材によって混色のしやすさが異なるので、お気に入りの組み合わせを見つけてみてください。
画材ごとのメンテナンスと保存方法
クレヨンみたいな画材は、保存方法にも工夫が必要です。パステルやコンテは粉が落ちやすいため、ケースや布で包むと良いでしょう。オイルパステルやクレパスは、直射日光や高温を避けて保存すると品質を保てます。
使い終わったら芯先の汚れを軽く拭き取ることで、次回もきれいな発色で描くことができます。長期間使わない場合は、湿気を避けてケースごと保管してください。
スケッチブックや画用紙の選び方
画材の特性に合った紙選びも大切です。パステルやコンテの場合は、表面に細かな凹凸(テクスチャー)がある専用紙がおすすめです。オイルパステルやクレパスには、厚みがあり表面がややざらざらした画用紙が向いています。
持ち運びやすさを重視するならスケッチブックタイプ、じっくり描きたいときは大判の画用紙を選ぶと良いでしょう。自分のスタイルや目的に合わせて、紙質やサイズを選んでください。
デッサン以外にも活躍するクレヨンみたいな画材の活用アイデア
デッサンだけでなく、クレヨンみたいな画材はさまざまな場面で活躍します。その応用例や楽しみ方を紹介します。
イラストや絵本制作への応用
発色の良いクレパスやオイルパステルは、イラストや絵本作りにもよく使われています。やわらかいタッチや温かみのある質感が、物語の世界観を豊かに表現してくれます。
また、背景やキャラクターの輪郭など、違う画材と組み合わせて使うことで、深みのある仕上がりになります。カラフルな表現を活かして、幅広い作風に挑戦できます。
工作やクラフトでの活用例
クレヨンみたいな画材は、紙だけでなく木材や布、段ボールなどにも描けるものもあります。季節の飾りやカード作り、手作り小物のデコレーションにもぴったりです。
たとえば、子どもの工作やプレゼントのラッピングに使ったり、オリジナルのしおりやコースターを作ったりと、アイデア次第で様々なクラフトに応用できます。
子どもから大人まで楽しめるアート体験
簡単に扱えるクレヨンみたいな画材は、年齢を問わず楽しめます。親子で絵を描いたり、友達同士でアートワークショップをしたり、気軽なアート体験にも最適です。
色を重ねたり、自由に表現したりすることで、創造力を育むきっかけにもなります。特別な技術がなくても始められる点も魅力のひとつです。
プレゼントやギフトにおすすめのセット
可愛いパッケージのクレパスセットや高級感のあるパステルセットは、プレゼントにも喜ばれます。子ども向けから大人用まで、贈る相手に合わせて選びやすいのもポイントです。
ギフト用には、持ち運びに便利なケース付きや、テーマに合わせた限定カラーセットも人気があります。アート好きの方や新しい趣味を始めたい人への贈り物にぴったりです。
人気メーカーとおすすめクレヨンみたいな画材ランキング
どのメーカーや商品を選べばいいか迷うとき、人気ランキングやクチコミも参考になります。ここでは初心者向けからプロ愛用まで、評判の高いアイテムを紹介します。
初心者向け人気ランキング
初心者におすすめのクレヨンみたいな画材ランキングは、扱いやすさや価格、カラーバリエーションを重視しています。
| 順位 | 商品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1位 | サクラクレパス12色 | 発色が良く手頃な価格 |
| 2位 | ぺんてるオイルパステル | 柔らかさと混色が簡単 |
| 3位 | ファーバーカステルパステル | ハードとソフト両方対応 |
どの製品も初心者が安心して使えるセットとして人気です。
プロ愛用のおすすめアイテム
プロや上級者には、色数が豊富で質感にこだわれるメーカーが好まれます。「レンブラントパステル」「カランダッシュネオパステル」「シュミンケソフトパステル」などは、発色や描き味に定評があります。
繊細なニュアンスや長時間の作業にも耐える品質の高さが、プロから支持を集めています。自分の作風や用途に合わせて選んでみてください。
話題の新商品や限定セット
最近は、期間限定のカラーセットやテーマ別のコラボ商品も増えています。たとえば、季節限定カラーやアーティストとのコラボセットなど、個性的なセットが注目を集めています。
新商品を選ぶ際は、使い勝手や既存の色と被らないかもチェックポイントです。限定感を楽しみながら、新しい表現にチャレンジできます。
クチコミやレビューで選ばれる理由
クレヨンみたいな画材は、実際の使用感やクチコミも重要な判断材料です。「発色がきれい」「手が汚れにくい」「収納が便利」など、選ばれる理由はさまざまです。
特にAmazonや文具専門店のレビューは、実際に使った人の感想が参考になります。気になる商品は、口コミをチェックしてから購入すると安心です。
まとめ:デッサンに適したクレヨンみたいな画材で表現の幅を広げよう
クレヨンみたいな画材には、パステルやコンテ、クレパスなど多彩な種類があり、それぞれに異なる特徴と魅力があります。自分の表現したいイメージや用途に合わせて、適した画材を選ぶことが大切です。
初心者でも扱いやすいセットや、用途に合わせた色数・硬さを選ぶことで、無理なくデッサンに取り入れることができます。使い方やメンテナンスにも気を配りながら、新しい画材で表現の幅を広げてみてはいかがでしょうか。さまざまなテクニックや応用も楽しみながら、アートの世界をもっと身近に感じてください。
世界70か国で愛されるコピック!
ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。












