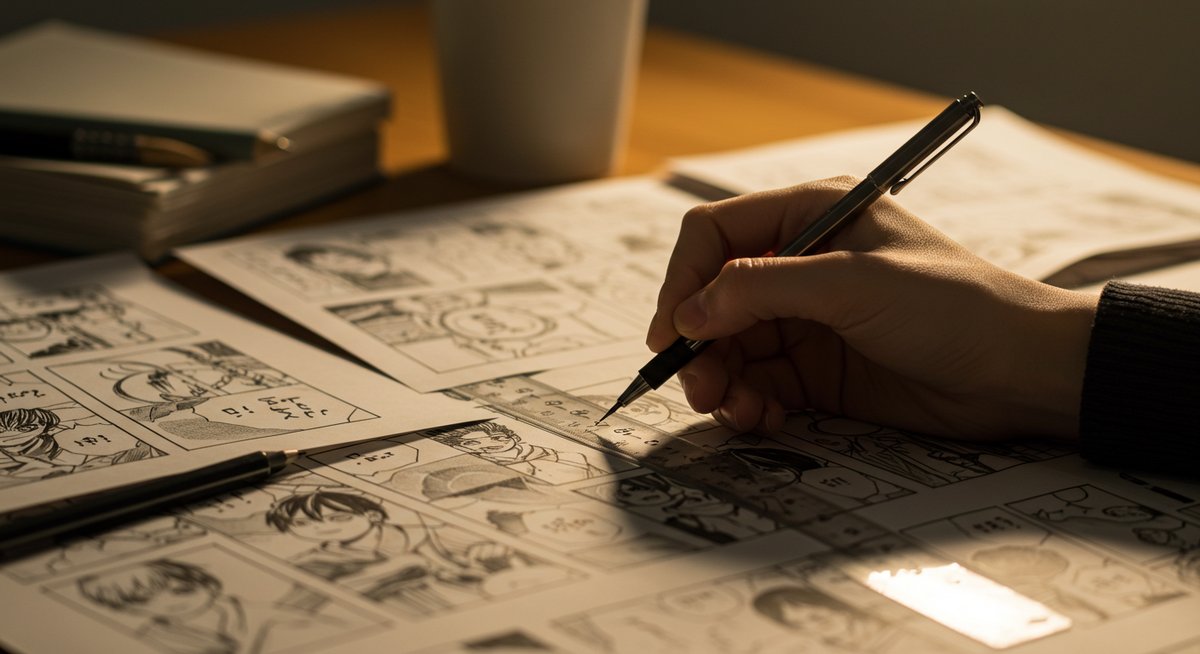漫画制作を始める際、多くの方が「物語の流れをどうまとめたらいいか」「どの画材を選んだら良いのか」と悩みます。章立てや画材選びは、物語を分かりやすく伝えるためにとても大切なポイントです。
作品の個性や読みやすさ、作業しやすさにも大きく関わるため、基本とコツを押さえておくことで、初心者から経験者までより充実した漫画制作につながります。まずは章立ての基本から順番に解説していきます。
漫画制作における章立ての基本とルールを知ろう

漫画の物語を分かりやすく展開させるには、章立ての役割やルールを理解することが欠かせません。ここでは、章立ての意味や構成パターン、その決め方のコツについて見ていきます。
章立てとは何か漫画における意味
章立てとは、長めの物語やシリーズ作品をいくつかのまとまりに分け、それぞれにタイトルやテーマを持たせる構成方法です。漫画の場合、物語の流れやキャラクターの成長、重要な出来事ごとに章を区切ることで、読者が内容を把握しやすくなります。
章立てをすることで「今どこを読んでいるのか」が明確になり、物語全体を通しての理解がしやすくなります。また、章ごとに盛り上がりや転換点を配置しやすくなるため、自然な構成や緩急も生まれやすくなります。
漫画の章立てでよく使われる構成パターン
漫画の章立てにはさまざまなパターンがありますが、代表的なものをいくつか紹介します。
- 時系列ごとに区切る(例:中学時代、高校時代など)
- 物語の課題や事件ごとに区切る(例:第1事件、第2事件など)
- キャラクターの視点ごとに分ける(例:主人公編、ライバル編など)
このように章立てを工夫することで、読者が内容を追いやすくなったり、物語のリズムが生まれやすくなります。どのパターンが作品に合うかは、物語のテーマや登場人物の数などによっても異なります。
章立てを決める際に意識したいルール
章立てを決めるときは、まず「一つの章が何を伝える部分か」を明確にすることが大切です。章の最初と最後で状況がどう変化するか、読者にどんな感情や情報を届けたいかを整理しましょう。
また、章ごとに話の盛り上がりや区切りを意識することで、物語にメリハリが生まれます。章が長すぎたり短すぎたりしないよう注意し、できるだけ均等なバランスを意識することもポイントです。
章とエピソードの違いを理解する
「章」と「エピソード」は混同されやすい言葉ですが、意味が異なります。章は物語を大きく分ける単位で、エピソードはその中の一つひとつの出来事や小さな話を指します。
たとえば「学校生活編」という章の中に、「入学式」「友達作り」「部活動」といった複数のエピソードが入るイメージです。章をしっかり区切ることでエピソードも整理しやすくなり、物語の流れをより明確にできます。
漫画の物語に最適な章立ての考え方
物語に合った章立てを作るには、まず全体の流れをざっくりと書き出し、どこで区切ると読みやすいかを考えることが大切です。大きな転換点や、キャラクターの成長の節目などを基準に章を設定する方法がおすすめです。
章ごとにテーマや雰囲気を少し変えることで、読者を飽きさせずに物語を楽しんでもらえます。まずは自分の描きたいストーリーに合った区切り方を探してみると良いでしょう。
「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!
著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。
画材の種類と選び方初心者からプロまで

漫画制作には多種多様な画材が使われます。ここでは、主な画材の種類やその選び方、初心者でも扱いやすいアイテムについて紹介します。
漫画制作で使われる主な画材一覧
漫画制作に使われる画材は、アナログとデジタルに大きく分けられます。ここではアナログ中心に、代表的な画材を表でまとめます。
| 画材名 | 特徴 | 用途例 |
|---|---|---|
| Gペン | 太細の線が描ける | 主線・髪の毛など |
| 丸ペン | 細い線が得意 | 細部・まつ毛など |
| ミリペン | 均一の線 | コマ枠・小物線 |
| インク | 黒く発色 | 線画全般 |
| トーン | 模様・陰影表現 | 衣服や背景 |
この他にも、消しゴム、定規、ブラシ、カラーマーカーなど用途に合わせていろいろな道具があります。自分の作風や作品のジャンルに合わせて選ぶとよいでしょう。
ペンやインクの種類と使い分け方
漫画でよく使われるペンには、Gペン、丸ペン、サジペンなどがあります。それぞれ線の太さや表現の幅が異なり、キャラクターの輪郭や背景、小物の細かい部分などで使い分けられます。
また、インクにも種類があり、耐水性や発色の良さなどで選ぶことが可能です。Gペンは力の入れ方で太さが変わるため、感情や動きを表現するのに向いています。丸ペンは細い線が得意なので、繊細な部分や仕上げにおすすめです。ペンの持ちやすさや自分が描きやすいと思うものをいくつか試してみるのが良いでしょう。
トーンやスクリーントーンの選び方
トーンは、画面に模様や陰影を付けるためのシート状の素材です。アナログ漫画では、衣服の柄や背景、キャラクターの影などを簡単に表現するのに使われます。
選ぶときは、柄の細かさや濃さ、使いやすいサイズをチェックしましょう。初心者の場合は、よく使うグレーのトーンや簡単な模様のものから始めると扱いやすいです。また、カッターで切り貼りする工程もあるため、失敗してもやり直しやすいシンプルなものを選ぶと安心です。
デジタル画材とアナログ画材のメリットデメリット
デジタル画材は、パソコンやタブレットと専用のソフトを使って描く方法です。アナログ画材に比べ、修正や複製が簡単で、さまざまな効果やブラシを選べるメリットがあります。一方、機材やソフトの初期投資が必要です。
アナログ画材は、手で紙に直接描くため、独特の質感や描き心地が魅力です。しかし、修正に手間がかかる場合や、インクや紙の消耗品コストがかかることもあります。どちらも一長一短なので、自分が続けやすい方法で選ぶのがポイントです。
予算別おすすめ画材セット
漫画制作を始めるときの画材選びは、予算に合わせて無理なく揃えることが大切です。下記はおすすめのセット例です。
| 予算 | セット内容例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 3,000円台 | Gペン・インク・トーン少量 | 最小限で練習用に最適 |
| 6,000円台 | ペン数種・インク・ミリペン・トーン | 多様な表現が可能 |
| 10,000円以上 | 画材一式+定規・カッター・消しゴム | 本格的な制作に対応 |
初めての方は、まず基本的な道具を使ってみてから必要なものを追加していくと失敗が少なくなります。
章立てと画材の関係表現力を引き出す工夫

章ごとの物語の雰囲気や展開に合わせて、画材の使い方を工夫することで表現力が高まります。ここでは、章立てと画材の関係性や、具体的な演出方法について解説します。
章ごとに変わる表現と画材の使い分け
物語が進むにつれて、章ごとに登場人物の心情や物語のトーンが変化する場合があります。その際、画材の選び方や使い方を少し変えるだけでも、読者に与える印象が大きく変わります。
たとえば、明るい章では柔らかい線や明るめのトーンを、シリアスな章では太めの線や濃いトーンを使うなど、画材の特性を活かして雰囲気を演出することができます。こうした工夫は、ストーリーの流れをより自然に伝えるのに役立ちます。
トーンや線の強弱で章の雰囲気を演出
トーンや線の強弱は、物語の雰囲気を左右する大切な要素です。感動的なシーンや衝撃的な場面では、トーンの濃淡を強調したり、線を太くして緊張感を高める方法があります。
一方、日常的でゆったりした章では、薄めのトーンや細い線を多用することで、柔らかく親しみやすい雰囲気を作れます。トーンや線の使い分けは、章ごとに演出したい気持ちに合わせて調整すると良いでしょう。
画材選びが作品の世界観に及ぼす影響
画材の選択は、作品の世界観やキャラクターの印象にも影響を与えます。たとえば、手描きの温かみが必要なファンタジー漫画にはアナログ画材が合う場合が多いです。
逆に、未来的な雰囲気や緻密な背景が求められる作品では、デジタル画材のほうが効果的なこともあります。自分の作品に合った画材を選ぶことで、描きたい世界をより魅力的に表現できます。
シーンごとに必要な道具のチェックポイント
章やシーンごとに使う道具は少しずつ異なります。たとえば、バトルシーンは太めのペンや濃いトーン、日常シーンは細ペンや薄いトーンなど、用途に応じて使い分けましょう。
制作前に「どんな場面でどの画材を使うか」をメモしておくと、作業がスムーズに進みます。チェックリストを作っておくと道具の忘れ物も防げて安心です。
章立てルールに沿った画材管理術
章が増えてくると、使用するトーンやペンなどの管理も重要になってきます。使った画材を章ごとにまとめて管理したり、消耗品は定期的に補充しておくと安心です。
また、デジタルであればファイル名に章の番号を付ける、アナログであればトーンやペンのストックを章ごとに仕分けしておくなど、管理方法を工夫すると作業の無駄が減ります。
実践漫画の章立てと画材選びのコツ

実際に漫画を制作するときに役立つ、章立ての分け方や画材選びの具体的なコツを紹介します。無理なく続けられるポイントを押さえておきましょう。
物語の展開を意識した章の分け方
章を分けるときは「物語の大きな流れ」や「キャラクターの変化」に注目しましょう。重要な出来事や転換点を基準に区切ると、物語が分かりやすくなります。
たとえば、冒険の始まり・仲間との出会い・試練・クライマックスといった形で章を設定すると、自然な流れになります。あらかじめゴールとなるシーンを決めてから、逆算して章を割り振る方法もおすすめです。
キャラクターごとに画材や表現方法を変えるテクニック
主要キャラクターごとに線の太さやトーンの種類を変えると、個性がより際立ちます。たとえば、主人公は明るいトーンや柔らかい線、敵キャラは濃いトーンやシャープな線で描くと印象的です。
一人ひとりの特徴に合わせて画材を工夫することで、登場人物が読者の中でより鮮明にイメージされやすくなります。描き分けが難しい場合は、資料や色分けシートを用意するのも効果的です。
読みやすい章立てを作るためのポイント
章立てを読みやすくするには、章ごとの長さや内容のバランスを意識しましょう。一つの章が長すぎるとダレやすく、逆に短すぎると物語が細切れになってしまいます。
- 章の目安は8〜16ページ程度
- 章ごとにサブタイトルを付ける
- 章の冒頭や終わりに印象的なシーンを配置する
これらを参考にすると、読者が先を読みたくなる構成を作りやすくなります。
章ごとの作業効率をアップする画材活用法
作業効率を上げるためには、章ごとに使う画材をあらかじめセットしておくのがコツです。たとえば、トーンやペン先を用途ごとに分けて準備しておくと、作業途中で迷わずに済みます。
また、デジタルの場合はブラシ設定やレイヤー分けを章ごとにテンプレート化しておくと、描く手順や修正がしやすくなります。効率的な画材管理は、締め切りがある場合にも役立ちます。
章立てのルールを守りながら個性を出す方法
基本的な章立てのルールを守りつつ、タイトルやページの見せ方、演出で自分らしさを加えることができます。たとえば、章タイトルに独自のフォントを使ったり、章ごとに雰囲気の異なるトビラ絵を描くと個性が際立ちます。
また、章の合間にイラストコラムやキャラクター解説を挟むのも良い方法です。基本を押さえつつ、作品のテーマや自分らしさを表現できる工夫をしてみましょう。
まとめ:章立てと画材で漫画表現をもっと自由に
章立ての基本やルール、画材の選び方を知ることで、漫画制作の幅は大きく広がります。物語の流れやキャラクターの個性に合わせて工夫することで、より魅力的な作品作りが可能になります。
これから漫画を描く方も、章立てと画材に少し意識を向けてみてください。自分なりの表現やスタイルを見つけることで、漫画制作がさらに楽しくなります。
世界70か国で愛されるコピック!
ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。